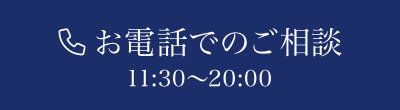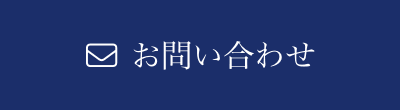お店や部屋の入り口に揺れる「暖簾(のれん)」。
この「暖簾」という言葉や文化が、どこから来たのか、その由来をご存知でしょうか?
歴史をたどると、中国禅宗からの影響や日本古来の布文化、商業の発展、そして老舗の想いまで、さまざまな背景が見えてきます。
このコラムでは、そんな「暖簾」の歴史を紐解きながら、現代にも続くその価値についてご紹介します。
目次
「暖簾」の語源と日本での由来
「暖簾」という言葉と、それに関連する日本特有の暖簾文化は、海外からの影響と日本固有の習慣が複雑に絡み合いながら形作られてきました。ここでは、その語源から日本で定着するまでの道のりを紐解いていきます。
中国禅宗由来の「暖簾」
「暖簾(のれん)」は、もともと中国の禅宗寺院の入り口に掛けた垂れ幕のことで、禅宗の用語でした。外と内、俗と聖を隔てる境界としての役割を果たすと同時に、日差しや風を遮る実用性も備えていました。
またこの暖簾は、簾(すだれ)に布を重ねた冬使用の幕を指し、夏になると布を取った「涼簾(りょうれん)」として、季節によって使い分けられたそうです。そして、布を重ねた「暖簾(のんれん)」という言葉と風習が、仏教の伝来とともに日本に伝わったのが由来だと言われています。
日本に上陸したばかりの頃は「のんれん」と発音されていましたが、時代の流れとともに「のうれん」と少しずつ変わり、最終的に今の「のれん」という呼び方になったと言われています。日本人の文化や口調に合うように自然と変化していった、というわけですね。
日本古来の布文化と中国文化の融合
さて、中国から「暖簾(のんれん)」がやってくる前から、実は日本にも古くから布を使って空間を仕切る文化がありました。日本の伝統的な建築様式が、屋根と柱によって構成された開放的な構造で、壁による仕切りが少なかったためです。
この仕切り布が高度に発展したのが、平安時代の頃だと言われています。「幌(とばり)」や「帳(ちょう)」と呼ばれ、主に貴族社会において、寝所や儀式の場を仕切るために使われていました。
鎌倉〜室町時代にかけては、禅宗寺院の影響を受けた質素な建築様式の中で暖簾が使われ始め、やがて町のお店にも広がっていきました。当初はこの暖簾を「幌(とばり)」と呼んでいましたが、禅宗文化の影響から「暖簾(のんれん)」という呼び名にだんだんと浸透していき、前述の通り、「のうれん」→「のれん」と変化していったそうです。
現代の日本に存在する暖簾は、日本人が昔から持っていた「布で空間を仕切る」という知恵と、中国禅宗文化が結びつくなかで、日本独自の道具として発展してきたものなのです。
暖簾の役割の変遷と色・形・素材の由来

暖簾(のれん)は、もともとは風よけや日よけ、目隠しといった実用的な目的で用いられてきました。しかし時代とともに、その役割やデザイン、素材にはさまざまな変化が見られます。ここでは、暖簾の歴史的な役割の変遷とともに、色・形・素材の由来についてもご紹介します。
時代とともに変化した役割の由来
平安時代の商業は、「市」という特定の日に開催される定期市が中心で、現在のような建物としての「店舗」はほとんど存在しませんでした。室町時代から桃山時代になるとお店を構える商売が増え、日差しや風を防ぐ実用品として店先に暖簾を垂らすように。そのうち、「今、お店が開いていますよ!」という営業中のサインとしても定着していきました。
江戸時代に入ると、文字や家紋を染め抜いた暖簾が登場。屋号や取扱商品を知らせる広告的な役割を持つようになりました。また、のれん分けという商慣習が生まれ、暖簾は「信用」や「伝統」の象徴として重みを増していきます。
明治時代以降、西洋から看板文化が入ってきたことで、暖簾が持つ広告的な役割はやや薄まってしまいましたが、特に長い歴史を持つ商店にとって、暖簾は世代を超えた商いのバトンであり、信用・実績・品質の証でもあるとして、ますますその価値に重きが置かれるようになったのです。
現在でもその文化は継承されつつ、さらに、空間を作るインテリアとしても活用されています。
暖簾の色彩の由来
暖簾に使われる色には、古くから商いにまつわる意味や用途が込められています。
たとえば藍や紺は、防虫効果と落ち着いた印象から呉服店や蕎麦屋などで好まれ、堅実で信頼感のある商売の象徴とされてきました。また、白は清潔感を伝える色として菓子屋や薬屋で多用され、赤は食欲を刺激する色として大衆食堂やラーメン店で親しまれてきました。
このように、暖簾はその色の違いによって、装飾を超えた商いのサインとしての役割も果たしていたのです。
【関連記事】日本の伝統製品「暖簾(のれん)」の意味や役割とは?
暖簾に描かれる文様や意匠の由来
暖簾には、屋号や家紋に加えて、さまざまな文様や意匠が描かれます。それらの文様や意匠は、ただの装飾にとどまらず、商売繁盛や、長寿を願う吉祥文様としての意味を持っています。
たとえば、「松竹梅」「鶴亀」「七宝」などは縁起の良い文様として、「麻の葉」や「青海波」などの幾何学模様は成長や平穏の象徴として親しまれていました。
また、魚や蕎麦などの業種を表すモチーフを入れることで、ひと目で商いの内容を伝える役割も担ってきました。
そして、こうした文様には、店の想いや歴史が込められており、暖簾はその店ならではの顔として、文化や伝統を今に伝えています。

暖簾の切れ目や丈の由来
暖簾には、居酒屋や料亭などでよく見る切れ目の入った暖簾から、目隠しを目的とした暖簾、長さが短く1枚の幕のようなデザインの「水引暖簾」、日よけのために店舗の軒先に張る「日除け暖簾」など、さまざまな形があります。
さらに、歌舞伎や日本舞踊などの楽屋口に使われる「楽屋暖簾」や、銭湯や温泉などの入り口に掛けられる「湯暖簾」、屋号やロゴではなく絵を入れて染め上げた「絵暖簾」、花嫁が輿入れする際に嫁入り道具として持参する「花嫁のれん」など、長い歴史の中で、少しずつ役割や形状を変えながらさまざまな暖簾が登場し、それぞれに想いが込められています。
たとえば、店先にかかっている切れ目が入った暖簾には、お客様がスムーズにお店に入ることができるようにと、お客様を歓迎する心が込められていると言われており、水引暖簾には、邪気を払う気持ちや縁を結ぶ想いも込められています。
【関連記事】暖簾(のれん)にはどんな種類がある?形状によって異なる呼び名とその特徴
素材・生地の変遷
暖簾の素材にも、その時代の技術や暮らしぶりが反映されています。日本では古くから麻が使われ、通気性や清涼感に優れたことから夏場の使用に適していました。江戸時代以降は、染めの表現に優れた綿が普及し、藍染めとの相性の良さから広く用いられるようになります。
現代では、耐久性や防汚性に優れたポリエステルなどの化学繊維も登場し、暖簾はさらに機能性を増しています。たとえば、「エステル麻」や「エステル帆布」などは、伝統的な風合いを保ちつつ、耐候性を備えた素材として、商店や飲食店に多く使われている素材です。
【関連記事】暖簾(のれん)に使われる生地・素材にはどんなものがある?それぞれの特徴や適した生地の選び方をご紹介
暖簾に込められた歴史に想いを馳せて
今回は「暖簾の由来」について、さまざまな視点からご紹介しました。
「暖簾(のれん)」は、単なる布ではなく、実用品として、そして文化的象徴として、長い歴史の中で日本独自の進化を遂げてきました。
現在は老舗の象徴にとどまらず、企業のブランディングや空間演出にも取り入れられるなど、ビジネスシーンでも新たな価値を発揮しています。
街角で暖簾を見かけたときは、ぜひその深い歴史に、そっと想いを馳せてみてはいかがでしょうか。
染物を通じてお客様の大切な「こだわり」をカタチに

水野染工場「日比谷OKUROJI店」は、北海道旭川で明治40年から染物屋を営む株式会社水野染工場が「より染物を身近に感じていただけますように」との願いを込めて東京で展開する染物専門店です。
手ぬぐいや藍染商品の販売以外にも、藍染のデモンストレーションや体験イベントを行うなど、藍染を通じてお客様の「想い」に寄り添う商品をお届けしています。
半纏・法被、暖簾、旗、手ぬぐい、帆前掛け、神社幟、神社幕…など、印染製品のオーダーメイドについても、直接店舗でご相談いただけますので、ぜひ一度、水野染工場「日比谷OKUROJI店」にお越しください。