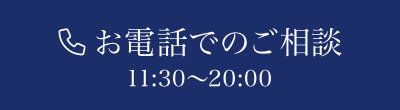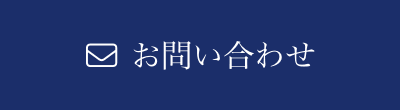日本の伝統的な着物には、さまざまな形状のものがあり、お祭りなどで見かける「半纏」もその一つです。しかし、この半纏は、一体いつごろからどういった意味で着用されるようになったのでしょうか?
今回は、そもそも半纏とは何か、その意味をまとめるとともに、歴史や「半纏」という漢字の由来、また具体的な着用シーンについて解説していきます。また、「法被と半纏は何が違うの?」「半纏とどてらの違いは?」という疑問をお持ちの方に向けて、半纏の豆知識もご紹介していますので、半纏についての知識を深めたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「半纏」の意味や漢字の由来とは
「半纏(はんてん)」とは、江戸時代に庶民が防寒着や仕事着として着るようになった上着のことを意味します。
もともと大名や武士などの上の階級だけに着用が認められていた「法被(はっぴ)」が庶民の間にも広まってしまったため、贅沢を禁じる奢侈禁止令(しゃしきんしれい)の一環として羽織を禁止・制限する法令を発令。その禁止令を犯さないように、庶民用の衣類として作られたのが「半纏」で、それが半纏の歴史の始まりだと言われています。
この「半纏」には、「袢纏」・「半天」・「伴天」…など、さまざまな表記がありますが、実は業界内では「袢天」が正しい表記だとされています。
もとは袖が半分、つまり半丁であることから「半丁(はんてん)」と呼ばれていたのですが、時を経る中でさまざまな意味を加えながら漢字表記が変化。正しい表記は「袢天」ですが、現代では漢字変換のしやすさから「半纏」が一般的に使われるようになりました。
【表記の変化例】
半天 :「半丁」から当て字へと変化
袢天・袢纏・伴天 :着物の肌襦袢から転じて変化
半纏 :“纏う”という意味が加わって変化
なお、「半纏」・「袢天」・「袢纏」・「伴天」・「半天」・「半丁」という表記は、一般的に使われている「半纏」の読みと同じように、どれも「はんてん」と読みます。
半纏を着る意味って?用途や役割とは?

江戸時代に庶民が羽織として着用を始めた半纏ですが、どのようなシーンで利用されているのでしょうか?ここからは、半纏がどのような意味や役割で着用されているのかをまとめていきます。
半纏を着る意味や役割①:防寒着
半纏は防寒着として着用されることも多いです。
特に中に綿を入れて作られた「綿入れ半纏」は、保温性も高く、冬の寒さをしのぐのにぴったり。現代でも冬の室内着として親しまれています。
半纏を着る意味や役割②:作業着やユニフォーム
半纏は、作業着やユニフォームとしても着用されています。
例えば、大工や植木屋・火消し・左官屋…など、主に職人が仕事着として着用することも多いのが特徴。半纏の背中や衿に屋号や紋・ロゴマークを入れて作られるため、そのような半纏は「印半纏」と呼ばれています。
また、江戸時代の火消しが仕事着として着ていた半纏は「消防半纏」と呼ばれており、消防は建物を壊して延焼を防ぎました。火消は刺子の厚手生地に水をかぶり濡れた半纏を纏いながら、火事場に飛び込んだのでいったのです。
なお、現代でも消防士が出初式などで着ている姿を見ることができます。火消し半纏(消防半纏)には、少しの火の粉では穴が開きにくい厚地の刺子が使用されることがあり、当社でも製作可能です。
半纏を着る意味や役割③:祭りや行事の衣装
私たちが目にすることが多いのが、お祭りやイベントの衣装としての半纏かもしれません。
特に祭り半纏や神輿半纏と呼ばれる半纏は、背中や衿に町内会や団体のロゴや名前を入れ、皆で着用することで一体感を出すことができます。
また半纏には、太鼓をたたきやすいように形に工夫がされた太鼓半纏や、店舗の販売やキャンペーンで着用される半纏などもあり、さまざまなシーンで活躍を目にすることができます。
半纏を着る意味や役割④:漁師の晴れ着
半纏には、漁師の晴れ着や正装として着用されることもあります。
晴れ着として着用される半纏は、「萬祝半纏(まいわいはんてん)」と呼ばれており、新しく造られた漁船を水面に下ろす進水式や豊漁の祝いの席、また船主の還暦祝いなどに使われます。
この萬祝半纏は、千葉県の房総半島が発祥とされており、現在は千葉県の伝統的工芸品として親しまれています。
半纏と法被の意味・呼び方の違い
防寒着や仕事着、祭りの衣装として着用されている半纏ですが、現代においては地域によって「半纏」や「法被」と呼び方が異なるのをご存じでしょうか?
もともと「半纏」は、武家などが羽織として着用していた「法被」を由来として、庶民用に生まれ変わったもの。しかし、江戸時代の末期ごろから区別がなくなり、現代では、衣類としての形状や着用シーンもほぼ同じとなっています。
ただ異なるのは、その名前の呼び名です。
この呼び名が変わる境界線と言われているのが、静岡県の大井川。この大井川を境にして、神輿を担ぐ東日本では「半纏」、山車を引く西日本では「法被」と呼ぶことが多いと言われています。
この「半纏」と「法被」の違いについては諸説ありますが、東と西で半纏の呼び名に違いがあるのも、長い歴史を経てきた半纏ならではの文化かもしれません。

半纏に似ている衣類
半纏と法被の違いについては先程お話ししましたが、半纏と似た形の羽織には、「どてら」や「ちゃんちゃんこ」と呼ばれるものもあります。
では、これらにはどのような違いがあるのでしょうか?
どてら
どてらとは、和服の上に着る防寒着のこと。綿が入っており、羽織りやすいように袖が広めに作ってあります。着丈は膝下ぐらいで、旅館で湯上りに浴衣の上に着るものと言えばイメージしやすいかもしれません。
このどてらは、布団代わりとして使われることもあります。綿が入っているので保温性が高く、どてらの背を体の前側にして袖を通すことで肩や首周りを覆うことができるため、冬でも暖かくして眠れるのです。
また、どてらは関東地方では「丹前」とも呼ばれており、江戸時代初期に堀丹後守の邸の前にあった町風呂、「丹前風呂」がその名の由来となっています。
ちゃんちゃんこ
ちゃんちゃんこは、綿を入れた袖なしの羽織のこと。綿が入っているので保温性が高く、主に子供や高齢者が防寒着として着用しています。
また、ちゃんちゃんこは長寿祝いとして使われることもあります。60歳の還暦を迎える方には赤いちゃんちゃんこ、70歳の古希を祝う場合には紫のちゃんちゃんこなど、年齢ごとの色を使ったちゃんちゃんこを着て、長寿を祝うこともあります。
さまざまな意味や役割を持つ半纏
江戸時代ごろから庶民の間で着用されるようになった半纏には、さまざまな意味や役割があることがお分かりいただけたでしょうか?
半纏は、現代においてもお祭りやイベントの衣装として、また職人さんの仕事着としてなど、街中で見かけることも多い日本の伝統的な着物の一つ。皆さんも半纏を着用する際には、ぜひ日本の伝統技術を用いたこだわりの半纏を注文してみてはいかがでしょうか?
私たち水野染工場「日比谷OKUROJI店」では、祭り半纏、神輿半纏、消防半纏、職人半纏、太鼓半纏など、お客様が纏うシーンに合わせた半纏・法被を職人が手染めで制作しています。店舗では、デザイン見本、生地見本、色見本などをご用意しているほか、対面打合せも可能。創業明治40年の伝統技術と知識で、あなたの「作りたい!」をカタチにします!
染物を通じてお客様の大切な「こだわり」をカタチに

水野染工場「日比谷OKUROJI店」は、北海道旭川で明治40年から染物屋を営む株式会社水野染工場が「より染物を身近に感じていただけますように」との願いを込めて東京で展開する染物専門店です。
手ぬぐいや藍染商品の販売以外にも、藍染のデモンストレーションや体験イベントを行うなど、藍染を通じてお客さまの「想い」に寄り添う商品をお届けしています。
半纏・法被、暖簾、旗、手ぬぐい、帆前掛け、神社幟、神社幕…など、印染製品のオーダーメイドについても、直接店舗でご相談いただけますので、ぜひ一度、水野染工場「日比谷OKUROJI店」にお越しください。